「……(シーン)」
参加者がうつむき、誰も口を開こうとしない。
ファシリテーターにとって、最も緊張感が高まる瞬間がこの“沈黙の会議”です。
でも安心してください。
この沈黙、「やる気がない」わけではありません。
多くの場合、参加者は「話してもいいのか分からない」「否定されそうで怖い」「どのタイミングで話せばいいかわからない」など、心理的なブレーキがかかっているだけなんです。
💡 原因1:安心して発言できる雰囲気がない
会議がピリピリしていると、自然と口を閉ざしてしまうのは当然のこと。
ファシリテーターはまず、「正解はない」「どんな意見も大歓迎」という安心感を場に届けましょう。
「なるほど、参考になります」「ありがとうございます」など、小さな肯定の言葉を積み重ねるだけでも、場の空気はぐっと柔らかくなります✨
💡 原因2:問いが抽象的すぎる
「どう思いますか?」という広すぎる問いは、意見を引き出すには不向きです。
参加者は「何から話せばいいのか?」と戸惑ってしまうからです。
例:
- 「A案とB案、どちらが実現可能だと思いますか?」
- 「〇〇の立場から見ると、懸念点はありますか?」
このように、問いを具体化するだけで、発言のハードルは一気に下がります。
💡 原因3:発言の偏りがある
会議では、どうしても話しやすい人に発言が集中してしまいがち。
逆に、控えめな人の意見が埋もれてしまうことも…。
そんなときは「書く参加」も有効です📝
付箋に書いて貼る、チャットで書き込むなど、声に出さなくても伝えられる手段を用意しておくと、多様な意見が引き出せます。
🎯 沈黙は「失敗」ではなく「チャンス」
沈黙が続くと焦りますよね。でも実は、それこそがファシリテーターの腕の見せ所。
- 空気をやわらげる
- 質問の切り口を変える
- 参加の形を変えてみる
そんな小さなアプローチの積み重ねが、意見を引き出し、対話を生み出す力になります💬


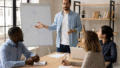

コメント